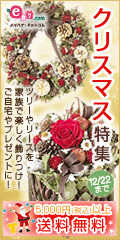いろんな情報を詰め込んだ!?すきなもの日記♪
GDIバール(03/02)
稼げる携帯アフィリサイトプレゼント小川(08/09)
こちらこそ、有難う御座います。SAI-BON(07/22)
コチラにはNNO(06/30)
ありがとうございます!NNO(04/10)
★ビジネスランキング100選★
からのコメント
カテゴリー
アーカイブ
最新記事
(12/14)
ふっかーつ
(02/28)
昨日の夜ご飯は!トマレピ!
(02/14)
マッサージに行ってきた!!
(10/15)
アロマコスメ 凛恋 がいい!
(04/05)
娘ちゃまのトイレトレーニング
広告エリア
ピックアップ記事
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
体験学習 というのは、小学校などで行われていたのじゃないかな?
というのは、小学校などで行われていたのじゃないかな?
私の記憶では。
私の小学生のころは、体験学習がかなりの割合を占めていたようなきがする。
たとえば、学校の周りで草花をさがす。
たとえば、校庭に出て、雲を観察。
たとえば、修学旅行先で集めた写真や資料を基に、新聞をつくる。
たとえば、グループで大凧をつくって揚げる。
たとえば、先生が切ってきた竹で、各自お箸を作る。
たとえば、わらで宝船を作る。
たとえば、田植え、稲刈りを体験する。
いまの小学校ではやらないのかな?
町の小学校では、できないことも多いか、、、、^^;
お箸を作ったとき、ナイフで手を切ったりもしましたが、ナイフがちゃんと使えるようになると、たのしくて鉛筆を削ったりするのにも、ナイフをつかったものです。
あぶない?いえいえ、使い方を知らないということが危ないのです。
きちんと使い方を知っていれば、危なくないはずでしょう?
授業よりも、かなりの割合で、、、私の中に記憶として残っているということは、子供にとってそれらはとても楽しめ、とてもいい経験になっているということ。
体験学習は、心に残りやすいのです。
Z会のプログラムでは、いろいろな体験学習を行っているみたい。
花を探して、押し花を作る
ミニトマトを育てる
雨の中を探検する
帆掛け舟をつくる
カレーを作る
七夕飾りをつくる
などなど、毎月季節にあった体験学習で、どれも親も一緒に体験したいな~とおもうくらい、楽しそう。
国語力検定というものがあるのだそうです。
国語力検定は、「読む力」「書く力」「聞く力」「話す力」「総合的国語力(=違う地域・違う時代の言葉の理解や一般的教養も含めた国語の力)」の5項目に分けて国語の能力を客観的に測る、新しい検定なんだそうです。
国語力 。今の子供たち、、、いや、自分も含め、おとなになってしまった人たちも、国語力は低いのじゃないだろうかと思ってしまいます。
。今の子供たち、、、いや、自分も含め、おとなになってしまった人たちも、国語力は低いのじゃないだろうかと思ってしまいます。
自分でも受けてみたいな。この検定。
もちろん、子供が小学生くらいなら、受けさせてみたいとおもいますね。
読む、書く、聞く、話す、どれも大事。
特に話す力、はわたしのニガテなところ。
大学時代、人前で話すこと、をテーマにした授業がありましたが、ほんとう~~~に緊張のれんぞくで、小さいころからそういうことに慣れておくことは必要だなぁ~とおもいました。
コミニュケーション不足、といわれる昨今、あなたのお子さんは、どうですか?
国語力検定は10~14歳のお子さんを対象にしているそうです。
※BloMotion・キャンペーン参加記事
 というのは、小学校などで行われていたのじゃないかな?
というのは、小学校などで行われていたのじゃないかな?私の記憶では。
私の小学生のころは、体験学習がかなりの割合を占めていたようなきがする。
たとえば、学校の周りで草花をさがす。
たとえば、校庭に出て、雲を観察。
たとえば、修学旅行先で集めた写真や資料を基に、新聞をつくる。
たとえば、グループで大凧をつくって揚げる。
たとえば、先生が切ってきた竹で、各自お箸を作る。
たとえば、わらで宝船を作る。
たとえば、田植え、稲刈りを体験する。
いまの小学校ではやらないのかな?
町の小学校では、できないことも多いか、、、、^^;
お箸を作ったとき、ナイフで手を切ったりもしましたが、ナイフがちゃんと使えるようになると、たのしくて鉛筆を削ったりするのにも、ナイフをつかったものです。
あぶない?いえいえ、使い方を知らないということが危ないのです。
きちんと使い方を知っていれば、危なくないはずでしょう?
授業よりも、かなりの割合で、、、私の中に記憶として残っているということは、子供にとってそれらはとても楽しめ、とてもいい経験になっているということ。
体験学習は、心に残りやすいのです。
Z会のプログラムでは、いろいろな体験学習を行っているみたい。
花を探して、押し花を作る
ミニトマトを育てる
雨の中を探検する
帆掛け舟をつくる
カレーを作る
七夕飾りをつくる
などなど、毎月季節にあった体験学習で、どれも親も一緒に体験したいな~とおもうくらい、楽しそう。
国語力検定というものがあるのだそうです。
国語力検定は、「読む力」「書く力」「聞く力」「話す力」「総合的国語力(=違う地域・違う時代の言葉の理解や一般的教養も含めた国語の力)」の5項目に分けて国語の能力を客観的に測る、新しい検定なんだそうです。
国語力
 。今の子供たち、、、いや、自分も含め、おとなになってしまった人たちも、国語力は低いのじゃないだろうかと思ってしまいます。
。今の子供たち、、、いや、自分も含め、おとなになってしまった人たちも、国語力は低いのじゃないだろうかと思ってしまいます。自分でも受けてみたいな。この検定。
もちろん、子供が小学生くらいなら、受けさせてみたいとおもいますね。
読む、書く、聞く、話す、どれも大事。
特に話す力、はわたしのニガテなところ。
大学時代、人前で話すこと、をテーマにした授業がありましたが、ほんとう~~~に緊張のれんぞくで、小さいころからそういうことに慣れておくことは必要だなぁ~とおもいました。
コミニュケーション不足、といわれる昨今、あなたのお子さんは、どうですか?
国語力検定は10~14歳のお子さんを対象にしているそうです。
※BloMotion・キャンペーン参加記事
PR
Comment
Trackback



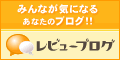


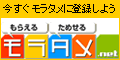
![[BloMotion]ブログで記事を書いて報酬をゲット!!](http://blomotion.jp/img/blogBnr-invite.gif)